藤野彰先生『「嫌中」時代の中国論』刊行記念インタビュー
8月発売の『「嫌中」時代の中国論』の著者、藤野彰先生に
本書を書かれたときのお話をお伺いしました。
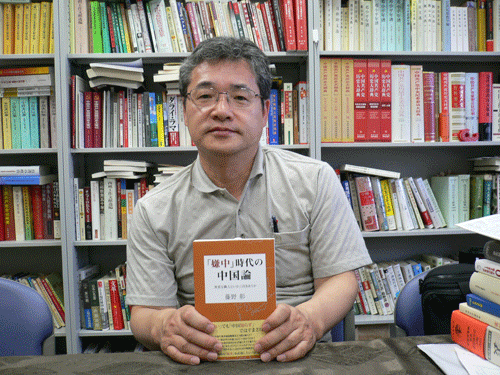
(著作『「嫌中」時代の中国論』を手にする藤野先生)
〈中国への関心〉
編集部 藤野先生は、いつから中国に興味を持たれていたのですか?
藤野彰先生(以下「藤野」) 中学生のときから関心がありました。
編集部 へえ、どうしてですか?
藤野 当時の中国は、非常に閉塞的な国で、「いったい、どういう国なんだろう」という好奇心からです。
編集部 中学生というと、日中交流は始まっていたのですか?
藤野 一定の日中交流はありましたが、まだ国交正常化される前です。国交正常化は1972年9月ですから、私が大学に入ったのは1973年、その翌年です。中国では1966年に文化大革命が始まりました。私が11歳のときです。大学に入ったときも、まだ文化大革命の時代です。とにかく、すぐ近くの国なのだけれども、もちろん簡単に旅行にもいけない。当時は友好団体関係者など特定の人たちでなければ、なかなか中国に行けませんでした。今のようにいろんな中国情報が溢れているという時代でもない。文字どおり近くて遠い国でした。非常に不可解で、ある意味神秘的で、いったい何が起きているのか、という素朴な関心がありました。
これが中学生のときから大学生まで、ずっと持っていた疑問です。何か特別なきっかけがあったわけではないけれども、とにかく近くの国で、何が起きているのかよく見えない、いったい何なのかという関心、これがそもそもの始まりですね。大学に入って第2外国語で中国語を選択し、2年目にはいきなり毛沢東(もう・たくとう)の論文を原文で読ませられました。今思えば、それが時代の空気だったのでしょう。
編集部 それは、新聞記者への道を歩まれたきっかけにもなっているのですか?
藤野 新聞記者になったというのは、中国問題と直接的には関係していないのですが、多少はつながっていると思います。新聞記者を30数年間やりましたけど、結果的にそのうちの3分の2くらいの年月は中国と関わる仕事で過ごしてきましたから、中国に対する関心は中学生時代から、ずっと今まで一貫して持ってきたという感じですね。
〈薄熙来裁判について〉
編集部 腐敗スキャンダルで失脚した元重慶市党委書記、薄熙来(はく・きらい)の裁判が行われていますよね。そのことについては、どのように見られていますか?(*インタビューは2013年8月26日、薄熙来裁判の最中。まだ判決は出ていなかった)
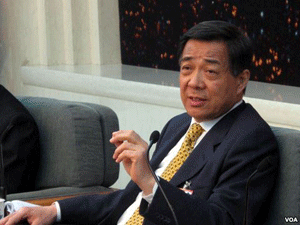
(薄熙来)
藤野 一つには政治ショーですよね。
編集部 政治ショー?
藤野 ええ。中国では、今回のような、元政治局員という高級幹部がかかわった裁判を行う場合、映像をたくさん流したり、あるいは外国人記者にも積極的に取材の便宜を図って公開したりということは普通やらないんです。ただ、習近平(しゅう・きんぺい)政権は腐敗撲滅を重要政治課題の一つに掲げています。このため、腐敗幹部に対してはその地位の高低にかかわりなく、法に基づいて厳しく処罰するといった姿勢を、国民に強くアピールしたいわけです。それによって、政権の威信や求心力を高めたい。いろいろな政治的配慮から、薄熙来の裁判を「政治的なドラマ」「政治ショー」にしようとしていると感じますね。加えて、裁判をテコに、薄熙来を支持する勢力を抑え込んでおきたいという思惑もある。やっぱり背景にあるのは権力闘争です。
編集部 裁判が行われる前から刑は決まっているわけですよね?
藤野 行われる前から決まっていると言えば決まっていると思います。このような政治事件では、裁判官が独自に自分の裁量で判断を下すことはできません。中国では三権分立が存在せず、司法機関も共産党の指導の下にありますから。指導部のなかで、どのくらいの量刑にするかということは、予め政治的な決定がなされている、方針が決まっている裁判だと思いますね。
編集部 それなのにどうして裁判をするのかな、というのが疑問だったんです。
藤野 一応、中国も法治国家ですからね。そういう建前がありますから。裁判もなしに刑務所にぶち込んでしまうということは、やはりできない話です。たとえ、形式的であれ、一応裁判をして公正な審議を尽くしたという手続きや、段取りは取らざるを得ないですね。
編集部 それを今回、公に見せているというのは、意図があってのことなんですね?
藤野 今回、薄熙来が問われているのは、いわゆる不正・腐敗といった類の罪状です。先ほど述べたように、共産党としては、元政治局員という非常に高い地位にあった人間であっても、万が一、重大な不正行為を働けば、厳罰に処するのだという厳しい姿勢、これを社会にアピールするというのが大きな狙いの一つです。
もう一つは、事件が起きたのは胡錦濤(こ・きんとう)政権時代ですけれども、現在の習近平指導部の方針と異なるような政治的見解、政治的路線を取ろうとする党内の動き、これは断じて許さないというメッセージですね。薄熙来はもはや過去のものになっている毛沢東の革命路線を礼賛する大衆運動を重慶で主導し、大胆にも党中央の権威に挑戦しました。しかし、民主集中制、上意下達の共産党体制のなかでは政治的なスタンドプレーは決して許されない。習近平指導部はそうした警告を国内向けに発しているのです。
編集部 『「嫌中」時代の中国論』で書かれていましたけど、共産党の上層部の人はかなり厳しい思想的なチェックを受けているわけですよね?
藤野 もちろんそうです。
編集部 それなのに、薄熙来は思想が違ってきたということですか?
藤野 もともとみんな共産党の一員ですから、原理原則上は、基本的な価値観というのを共有しているはずです。しかしながら、共産党は8300万人の巨大組織であり、実際には思想的にも右から左まで様々な考えの党員を内部に抱えています。たとえば、指導者が10人いたとして、いろいろな政策の進め方、何に重点を置くか、どう進めるかということについて、10人全員の意見が完全に一致するということはあり得ないことです。当然ながら、指導者の間でも意見や姿勢にズレが生じてくるはずなんです。これにライバル関係、権力闘争が複雑にからんでくる。
かつての、毛沢東と鄧小平(とう・しょうへい)の間でもそうです。政治家としての思想や行動スタイルにこれはもう水と油と言っていいくらいの違いがあったわけですね。今は「改革・開放」の時代になっていて、「改革・開放」という大きな路線そのものに異議を申し立てる人はごく少数ですけれども、「改革・開放」自体にしても何を優先するのか、どれをどのようなスピードで進めるのかということについては、指導者の間にやはり意見の食い違いはあります。ただ、共産党は建前としてそういう内部の意見の食い違い、あるいは対立というものの存在は認めないし、外部にも公開しないわけです。それはすべて内部の話であって、密室で処理すべき問題であり、公開するものではないという建前があるわけですね。しかし、実際には内部における対立がある。そして今回の薄熙来事件のような形で、ひずみが噴出してしまうのだと思います。
もちろん、薄熙来が本当に今の「改革・開放」路線に反対で、毛沢東時代にまた回帰すべきであると考えていたのかというと、そんなことはないと思います。なぜ毛沢東の革命路線を称えるようなことをしたのかというと、自分の政治家としての独自性、求心力、影響力を世間にアピールするためです。一般国民の間には「改革・開放」の負の側面である貧富格差拡大や幹部の腐敗蔓延に対する強い不満があり、その反動として「平等」「清貧」を旨とした毛沢東時代への郷愁のようなものが存在しています。薄熙来はそんな庶民感情を利用して政治家としての自らの市場価値を引き上げようとした。昨年秋に共産党の第18回大会が開かれましたが、そこでの最大の焦点であった最高指導部(政治局常務委員会)人事に向けて、自分に有利な政治環境を作りたいという彼個人の野心もあったでしょう。だから、政策や路線の違いと言っても、黒か白かといったような極端な違いではないと思います。
編集部 支持を集めたかったということですね。
藤野 はい。あるいは自分の庶民人気を煽りたかった。そういうことがあったと思います。というのは、中国の社会にはいろんな不満が渦巻いているわけです。特に大きな不満の一つはさっき言った貧富格差拡大なんですね。社会主義体制にもかかわらず、日本に比べれば、天文学的数字の格差です。多くの人がこれに対して強い不満を持っている。この不満というのは、共産党指導部に向けられることになります。要するに、共産党の政策がこういう事態を招いてしまったということですから。言ってみれば、薄熙来は、そういう庶民の現政権に対する不満をテコに、自分の庶民人気を高め、権力基盤強化の追い風にしようとしたということだと思います。
〈中国はなぜ、反日教育をするのか〉
編集部 中国では反日教育が国策で行われているように思うのですが、そういう国と日本はどのように付き合っていけばいいのでしょうか?
藤野 中国自身は反日教育をやっているとは言っていません。決して反日教育ではないと否定しています。ただ、歴史の記憶は次の世代にきちんと引き継いでいかなければいけない。そのための教育はやらなければいけないと主張しているわけです。
問題は、この歴史教育の中身です。中国共産党政権は国民の自由選挙で選ばれた政権ではないんですね。革命という名の、武力による政権奪取の結果、共産党が指導する中華人民共和国という国ができあがったわけです。つまり、選挙をして、民意によって政権が成立したわけではない。では、何によって共産党政権が中国を統治することの「正統性」が担保されるのか、という問題が出てきます。
共産党の理屈はこういうことです。日本の侵略軍が大陸でさんざん悪いことをした。それに対して共産党は戦った。もちろん、日中戦争の中国側の主力は国民党軍であったわけですが、共産党の歴史観では共産党軍が勇敢に戦って最終的に日本の軍国主義に勝利して、中国の自立・独立を達成したということになっています。共産党が今も政権を握っていることが正当化されるのは「救国」という歴史的貢献があったからであり、それこそが共産党政権の「正統性」である、というのが彼らの考え方なのです。
編集部 なるほど。
藤野 だからこそ、共産党は人民から支持されているし、この国を治める資格がある、というのが彼らの論理です。とすると、そういう論理を支えているのは何かと言えば、やはり「日本の侵略軍を打倒した」という歴史です。
編集部 そうなりますね。
藤野 その歴史は、彼らにとっては政権を支える大きな屋台骨ですから、なおざりにはできない。この歴史は徹底的に国民に教えこまれます。共産党があったからこそ、今日の繁栄した中国が存在しているのだと。したがって、学校教育では、歴史教育が非常に重視されます。特に近現代史ですね。中国の近現代史というと、どうしても日本という国が非常に重要なアクターになってしまうんです。もちろん、「悪役」ですね。日清戦争に始まり、日中戦争に至るまで、隣の「悪役」を抜きに中国の近現代史は語れません。それをどういうふうに語るかと言うと、日本は中国に攻めこんできた帝国主義、軍国主義の悪辣なシンボル的存在なんです。これと正面から戦ったのが共産党。そういう歴史観で教育が行われる。共産党の功績を称えることと連動して、日本がいかに中国においてひどいことをやったかという歴史の記憶が反復的に強調される。こういう政治環境、教育環境のなかでは、やはり反日的な感情が刺激され、増幅していかざるを得ないということですね。
編集部 そういうことなのですね。
藤野 歴史の事実として、日本が中国に侵略したということは否定できないと思います。他人の家に土足で上がって、人は殺すわ、物は盗むわ、ひどいことを散々やってきたわけですから、中国が被害者としてその歴史を後世に伝えるということは当然です。日本人がそれに対して異議を申し立てることはできない。歴史は忘れてはいけないし、直視し、そこから教訓を汲み取るべきです。しかしながら、現在の国家間関係というのは、歴史だけで成立しているわけではないですからね。60数年前の歴史、これが現在と未来の日中関係のすべての前提になってしまったら、あるいは日中交流のすべての基礎になってしまったら、日本と中国の関係は正常な形では進まないと思います。ただ、中国においては、そういう形で歴史教育が重視されて、特に日本との軋轢の歴史、これに力点が置かれている。結果として国民の間に反日的な感情というのがずっとくすぶっているという現状があるわけですね。
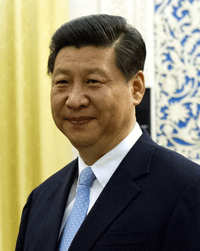
(習近平)
〈日中の理解を深めるには〉
藤野 過去の歴史は事実としても、戦後の日中関係の歩み、あるいは関係強化の成果に対する評価が中国側では非常に低調なのです。たとえば、日本は戦後60数年、対外的な戦争を一度も行わずに、平和国家として経済を中心に発展してきました。これに対して、中国が肯定的な評価をしているのかというと、必ずしもわれわれが期待するような評価にはなっていない。いまだに、「日本軍国主義は警戒しなきゃいけない」といったような声が中国側にはあるわけですね。中国の今日の経済発展をもたらした「改革・開放」を促進するうえでも、日本からの経済協力・技術支援は大きな役割を果たしてきたわけです。これは政府開発援助(ODA)などの形で中国に提供された。これに対する中国側の評価も高いとは言えません。もっとも、中国側には、日本の経済協力は中国が戦争の賠償請求を放棄したことの穴埋めとの認識があるので、そんなに感謝しなければいけないのかといった反感があるのでしょう。
編集部 中国の国民には、対中ODAなどの実績はあまり知られてないんですよね。
藤野 よく知られてないですね。中国国民には、中国の「改革・開放」の推進にあたって日本からのいろんな援助、支援がどういう働きをしたのか、どういう貢献をしたのかということは、十分に認識されていない。つまり、日本との関係をめぐる評価がアンバランスだということですね。歴史教育を行う一方で、戦後日本の平和主義、国際貢献についても、しっかり教えてくれているというのであれば、ある程度バランスの取れた日本のイメージ、日本観が形成される可能性もあるのですが……。現在のように、あまりにも一方に偏りすぎた教育――この教育というのは社会教育もそうですし、あるいはメディアを通じた報道の世界でもそうなのですが――やはり非常にバランスを欠いていると言わざるを得ないと思います。
編集部 付き合い方としてはどうすればいいでしょう?
藤野 まず日本人は、中国のそういう現状、たとえば日本に対する誤解なり偏見なりが渦巻いているという状況、そういう現実をまず理解しなければいけないですね。それを知らないまま、「中国は勝手なことばかり言っている」と嘆いても仕方ないです。中国ではなぜそういう反日的な言動が折に触れて噴出するのか、そういうメカニズムをまずは理解しないといけないですね。中国には中国の一応の論理があるわけです。もとより、それが日本人から見て、好ましいものか好ましくないものかという問題はあります。それは脇に置くとして、一応の論理があることは認識すべきです。それは何なのかということですね。その実情と背景、まずそれを直視するということが重要だと思います。
次の段階として、誤解、あるいは偏見があるとすれば、それをできるだけ解いていく努力、緩和していく努力というのが必要ですね。これは日本側から積極的に行わなければならない。そういう努力をこれまで十分やってきたのかと言うと、まだ足りないところがあると思います。日本からもっと情報発信をする。日本の立場・見解をもっとわかりやすい形で伝えていく。残念ながら、日本人は政府も民間も、意識的にそういう努力を十分にしてきたとは言えないと思います。
編集部 具体的にはどうしたらいいのでしょう?
藤野 もちろん、日中間の個人的な交流は、40年前に比べれば、比較にならないくらい広がってきています。そういう民間レベルの個人的な交流というのは、確実に両国関係のベースになるものですね。一番大きい問題というのは、なんとなくお互いに相手のことをわかっているというふうに思い込んでしまうところですね。
編集部 確かにそうですね。
藤野 これは日本人も中国人もそうなんです。自分の断片的な知識とか、聞きかじりの情報やメディアの報道だとか、そういうものを元に自分で勝手に都合のいいイメージを描いて、それでもって相手を非難する、こうだと決めつけてしまうという傾向がどうしても強いですね。やはり、これは改めていかないといけないと思います。特にこの問題においては、相手国に関する両国民の主要な情報源であるメディアが果たさなければいけない役割が大きいですね。
加えて、草の根レベルの交流が非常に重要です。中国からたくさん留学生が来て、日本の現実を自分の目で見て、自分の頭で判断して、理解してくれる。こういった地道な交流の積み重ねこそが不可欠です。草の根レベルの交流は広まってきていると言っても、ほんのここ数十年の話です。加速度的にそういうルートというか、パイプが広がったのは、せいぜいここ十数年でしょう。だから、日中の長い交流史のなかでとらえれば、本当に始まったばかりと言っていい。まだまだこれから積み重ねていかなければならないものがたくさんあると思います。
〈中国人留学生が抱いている対日感情〉
編集部 反日教育を受けていながらも、日本に留学に来たいと思うのはなぜでしょう。
藤野 それはもう、いろんな動機があると思います。ただ単に、反日的な教育を受けたから単純に日本を否定してしまうということではないんです。一方で、中国の若者たちは日本のサブカルチャーには子どものときから親しんでいるわけですね。そういうものを通じて、日本に対して親近感は持っている。だから、心のなかに反日的な感情の部分と、日本に対する親近感の部分とが共存しており、ない交ぜになっているという状況じゃないでしょうか。どちらか一つの感情だけ、つまり、反日しかない、あるいは日本に対する親近感しかないということじゃないと思いますね。
編集部 両方の感情を持っているというのは、日本人にも言えるかもしれないですね。
藤野 日本に対する感情というのは、そういう意味ではちょっと複雑な状況にあると言えると思います。子どものときから日本のアニメを見て育って、日本はいいな、一度本場の日本でアニメだとかファッションだとかを体験したいな、と思っている若者であっても、もし反日の嵐が吹き荒れたら、自分はまったく関係ない、そんなの興味はないと100人が100人そういう部外者的な立場を取れるかと言うと、それは疑問ですね。
編集部 そうですね。
藤野 やはり、どの国にも社会の支配的なムードというのがありますから。それとまったく無縁でいたいという人もなかにはいるかもしれませんが、そういう影響から完全に逃れるというのは、これもまた難しいことでしょうね。
〈日中外交について〉
編集部 中国に対する今の日本の外交をどう見られていますか?
藤野 一種の閉塞状況というか、打破する道筋を見つけられない感じですね。具体的には尖閣諸島の問題ですけれども、一つ重要なのは原理原則、日本の原則的な立場がぶれてはいけないと思いますね。中国に対して自分たちの主張はきちんと述べながら、交渉していくということですね。中国という国は、相手側にいろんなボールを投げてきます。言葉は悪いですけども、おどし、すかしを含めて。それは戦術的な側面ということもあるわけですから、中国の本音、あるいは個別の問題で言えば、落としどころは何なのか、そういうことをよく見極めていかなきゃいけないですね。
中国はしょっちゅう日本に対して怒っていますよ。過激な日本批判の声明を発表したり、メディアもそれに同調したり、というように。もっとも、これは戦術的にやっている側面が多分にあるわけで、文字どおりそれを真に受けて、こちら側がカリカリ怒ってもしょうがない。ですから、大事なのは、中国の本音は何か、そうすることによって彼らが何を狙っているのか、ということをよく読んでいくということですね。冷静に構えて挑発に乗らない、というふうに言い換えてもいいと思います。
編集部 今の安倍政権は、うまく読めていると思いますか?
藤野 うまく読めているかどうかはわかりません。わかりませんけども、対話の一応のルート、外交ルート、これはもちろん続いています。途切れているわけではないので、これを少しずつレベルアップし、首脳レベルの対話へと繋いでいってもらいたいですね。
それと、政治レベル、外交レベルの日中関係と、それ以外の日中関係、たとえば経済、文化交流、スポーツ交流などをきっちり分けるということですね。政治的、外交的な日中間のトラブルの影響を、ほかの分野にできるだけ波及させないような体制を取るということです。少なくとも、日本側からはそういうことをしない。これは明確にポリシーを維持していくべきだと思います。
ところが、中国はなかなかそうならないんです。昨年の尖閣騒動のときもそうですけど、政治関係が悪くなると、経済関係にも民間レベルの交流にもすぐ影響が及んでくる。予定されていたいろんな日中間のイベントや活動がキャンセルになりましたね。中国に対しては、もうそういうことはやめてほしいと思います。政治問題は政治問題、外交問題は外交問題として区別し、日中関係の悪化を他分野にまで拡大させることは自重してもらいたいと思います。
ただ、中国の体制からすると、実際にはそれが難しい。党と政府による仕切りが圧倒的に厳しく、多様な言論が容認されていませんから。少なくとも日本側から、中国と同じ土俵に上がってしまう付き合い方だけはしてはいけない。あくまでも政治問題は政治問題として扱い、総体としての日中関係のあるべき姿を見失ってはいけないということです。日本側としては中国に対して常にドアがオープンであるということ。そういう立場はしっかり守っていくことが重要だと思いますね。
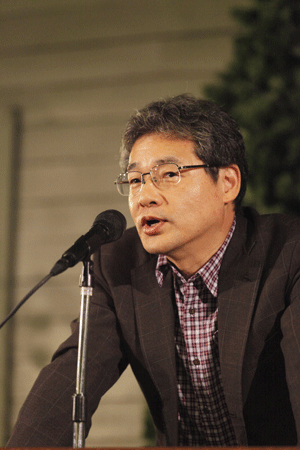
(013年10月12日「第4回 鈴木邦男シンポジウム」で講演する藤野彰先生 撮影:小森学)
〈領土問題について〉
編集部 領土をめぐる対立の解決はどうすればいいのでしょうか?
藤野 過去のケースを見れば、わかりやすい解決法というのは戦争ですね。国境線というのは戦争によって変更されたケースがほとんどです。かつてはロシアがアラスカをアメリカに売却したというようなこともありましたけど、今の時代ではそれはあり得ないですね。
編集部 ロシアと中国の間の国境問題は解決しているわけですよね。
藤野 これは交渉によって決着しています。要するに、フィフティー・フィフティーの痛み分けの形ですね。中ロの東部国境ではハバロフスクの向かいにあるアムール川の大ウスリースキー島(中国名=黒瞎子島)の領有権が最大の難題でした。この島はもともとロシアが実効支配していましたが、交渉の結果、中ロで分割することで合意しました。戦争によって、武力によって問題を解決するというのは、いまの時代、どの国でもそんなことは望まないし、仮に武力に訴えたら、とてつもないコストがかかることになるので、最も拙劣なやり方です。これは絶対に取るべきではないと思います。もちろん、相手国から一方的に先制攻撃されたとなれば、話は別になりますが。武力による解決というのは、少なくとも尖閣を実行支配している日本としては、自らが取るべき選択肢ではないですね。とすると、話し合いしかないです。
編集部 話し合うには、領土問題があると認める必要がありますね。
藤野 少なくとも領土をめぐる意見の対立がある、トラブルがあるということは認めざるを得ないと思いますね。
編集部 今は何も認めていない状態ですよね。
藤野 領土問題自体が存在していない、というのが日本政府の基本的立場ですから、尖閣諸島の帰属について、それを議題として中国と話し合うという用意は日本側にはないわけですよね。ただ、今の事態は一触即発と言ってもいい非常に危険な状態なので、この事態を避けるために双方がパイプを維持する、そこで最悪の事態を回避するために、双方ができることをやる、そういう話し合いは必要です。
私がこの『「嫌中」時代の中国論』で提案したのはこういうことです。中国側に異議があるのであれば、国際司法裁判所に提訴したらいい。そういうことを日本側が主張する、呼びかけるということです。そういうオプションがあってもいいのではないか、と思います。中国が自ら国際司法裁判所に提訴する可能性は、今のところほとんどゼロです。中国側は、二国間での解決を目指すべきで、問題をそれ以上国際化すべきではない、という立場ですから。中国側にそういう呼びかけをすることの実質的な意味があるのかという意見は当然あると思いますが、実は国際ルールに従って話し合いで国際的な紛争を平和的に解決していくということは日中間の合意事項でもあるんです。日中間で問題が起きたときには武力を使わずに平和的に解決していこうというのが、日中国交正常化の共同声明の精神であり、日中平和友好条約の精神でもあるわけです。ですから、この基本線はお互いに尊重しなければいけない。
じゃあ、そのための具体的な方法は何があるのかと言ったら、日中間で直接話し合うというのがもちろん一つですけれども、もう一つはそれで埒が明かなければ国際司法の場に判断を委ねましょうということです。ただし、実効支配している日本側から一方的に提訴する必要はまったくありません。
編集部 日本は、国際的なアピールが弱いような気がするのですが。
藤野 それはあると思います。
編集部 中国は、アメリカで領有権主張の広告を新聞に打ったりしていますよね。
藤野 中国共産党は、伝統的にいわゆる宣伝工作を重視してきましたから、国際宣伝戦略が巧みなんですよ。迅速に対応できる体制があるし、組織力もある。そもそも政権にそういう意思決定があるわけですね。対外宣伝予算だって日本と中国ではケタが違うんです。日本はこういう財政状況のなかで予算が削られてきていますけれどもね、中国は国益上、必要とあらば、思い切って資金や人力を投入する。ですから、パフォーマンス上の落差が出てきてしまうというのも致し方ないところです。ただ、尖閣の問題が国際的な注目を集めたこともあり、日本政府も対外宣伝をもっとしっかりやっていかなきゃいけないな、という考え方には変わってきてますよね。
編集部 自国の領土は1ミリたりとも渡してはいけないと思いますか?
藤野 それは状況によると思います。
編集部 いま領土問題がいろいろありますけど、ケースバイケースということですか。
藤野 大原則としては、領土を安易に他国に譲るということはあり得ない話ですね。ただし、これは利害得失の比較考量だと思います。長期的に見て、日本全体の国益にとってそれがプラスなのかどうかということによると思います。1ミリも譲らなかったために戦争になって、逆に膨大な、回復不能なほどの損害をこうむることだってありますから。いま中国と日本が戦争をやっていいことなんて何もないですよ。
北方四島にしてもそうだと思います。四島とも日本固有の領土であり、四島一括返還は譲れない――これは大原則の話としてあります。ただし、それこそ1ミリも、1センチ四方もロシアに対してまけることはできない話なのかどうか。あんまり硬直的な考えに凝り固まってしまったら、永久に解決できないかもしれない。「不法占拠」であるにしても、ロシア側にだって国内の政治情勢、世論、メンツというものがあります。だから原則は原則、実際の交渉、決断においてはやはり柔軟な思考もできるということでなければいけないと思います。
たとえば、中国が鄧小平時代に、イギリスから香港を取り戻すときに、いろんなやり方を考えたわけです。最終的にどういう方式にしたかと言うと、香港は返してもらう、ただし中国本土の体制とは違う「特別行政区」として返還後50年間は現行の制度を変えない、つまり香港の資本主義システムは変えない、言論の自由も守るということ、それを条件にしたわけですね。そういう発想ができるというのは中国共産党の非常に柔軟なところだと思います。もともと香港は中国のものなのだから、イギリスから返してもらったら、すぐ香港のシステムを社会主義に変えてしまえ。もし、そんな政策を共産党が主張していたら、香港は中国に平和的に戻って来なかったでしょう。無理矢理取り戻したとしても、暴動が起きて統治できなかったでしょうね。
編集部 なるほど、やり手なんですね。
藤野 原則は原則、実際の政策、決断にあたっては柔軟に対応するということです。これは一つのヒントにはなりますよね。
編集部 でも共産党の歴史観から見ると、尖閣問題は共産党にとっても大事ですよね。
藤野 共産党にとっては大事です。中国側はもちろん島が欲しいわけですけど、今は日本が「占領」してしまっている。日本は中国から島を「盗んで占領してしまっている」というのが中国の論理ですから。「しょうがないな」で済む話ではないんですよ。だって、共産党が政権を握っているからには、共産党は中国の領土を守らなければならない。台湾を含め、「祖国統一」の大業を完了しなければならない。いろんな強国、列強の侵略を跳ね除けて新しい国を作ったわけですから、領土問題で、しかも「不当に占領されている」と認識している領土、それについて共産党が簡単に譲歩するということはあり得ません。「日本に譲る」と言った段階で、共産党の正統性が音を立てて崩れてしまいます。だから中国は強硬姿勢を崩すことはできない。領土に対する認識というのも、中国と日本では本質的なところが違いますね。
編集部 そうですね。
藤野 日本人のなかには「尖閣諸島なんて誰も住んでいない小さな島だから、中国にくれてやったっていいじゃないか」という人だっているかもしれない。あるいはまったく無関心な人もいるでしょう。中国共産党と中国人のメンタリティーからすると、そんな考えはあり得ないです。ましてや相手は「宿敵」の日本ですから。そういう民族感情が尖閣問題に関しては余計に事態を複雑にしてしまっているということです。
どっちにしても、今日明日、すぐ何らかの解決の糸口が見つかるという話ではないんです。だから、今後も相当の長期にわたって、日中間で揉めつづける問題であるということをしっかり認識し、対応していかないといけないですね。今のところ、来年には日中関係がまたよくなるだろうとか、そういう楽観的な展望はできないと思います。
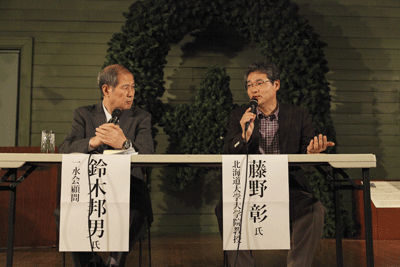
(2013年10月12日「第4回 鈴木邦男シンポジウム」で鈴木邦男氏と対談する藤野彰先生 撮影:小森学)
〈中国憲法について〉
編集部 話は変わりますが、自民党の憲法改正草案に出てくる「公益及び公の秩序に反しない」という表現と、本書『「嫌中」時代の中国論』に出てくる中国の憲法の表現が少し似ているなと思いました。
藤野 中国憲法35条ですね。
編集部 そうです。言論の自由を認める35条が51条の「国家、社会、集団の利益、及びほかの公民の合法的な自由と権利を損なってはならない」という表現で、骨抜きにされてしまっているというからくりがあると。ここを読んで、自民党の憲法改正草案を思い出しちゃったんです。
藤野 日本の場合は仮にそうなったとしても、憲法の解釈というのは政権にあるわけじゃなく、裁判所での判断になってくるわけですよね。自民党であれ、他の政権であれ、裁判所にこういう解釈にせよと命令することは日本のシステムではできませんから、ただちに中国のようになるということはないと思います。ただやはり、国の制度というのを自分の望むような方向に持っていきたいと考えている権力者というのは、いろんな細工をするであろうと思います。そこはもちろん要注意ですね。中国はそもそも三権分立制度がないわけです。憲法においても、一方で言論の自由を認めていながら、もう一方でそれを骨抜きにしてしまうような条文を挿入することによって、いかようにも解釈・対応できる形にしているのです。
編集部 中国では言論の自由は一応、認められているんですよね。
藤野 もちろんあくまでも憲法の条文の話で、建前としてはそうなっている。しかし、実態は違います。昨今の状況を見ていると、言論の自由、報道の自由についてはますます規制が厳しくなってきていますね。
〈歴史認識の共有はできるのか〉
編集部 今後、日中で共通の歴史認識を持っていくことは可能でしょうか。
藤野 それは無理です。100年後、200年後の将来にわたって絶対に無理、とまでは言えませんが。200年経てば、いくらなんでも日中戦争は完全な過去でしょう。その時には、今よりももっと冷静に、お互いに歴史を客観的に判断できるだろうと思います。そこまで時間がたてば、状況は変わっていると思いますが、10年、20年の間にお互いの見解をすり合わせて一致できるかと言ったら、それはちょっとできない話だと思います。
編集部 ドイツとフランスが同じ歴史認識ではなくても、共通の歴史教科書を作っているそうです。この事件に対しては、ドイツはこう考え、フランスはこう考えているという両側からの歴史観をドイツの生徒もフランスの生徒も一つの教科書で学んでいるそうです。(*邦訳『ドイツ・フランス共通歴史教科書』明石書店)
藤野 そういう複眼的な教育は日本でもあってもいいと思います。たとえば、南京事件について日本の教科書でも触れていますね。中国でどのような評価になっているかということについて、同時に日本の子どもたちに教えるということは、当然あっていい。ただ、現状では日中が共通の同じ教科書を使用するというのは難しいのではないでしょうか。お互いの政治制度も歴史観も価値観も違うので、それはかなり実現困難だと思います。歴史をどう見るかというのは民族や国家によって、立場が違えば、当然変わってくるわけです。同じでないというのが普通ですからね。しかし、どう違うのかという点について、あるいはなぜ違うのかということについて、きちんと理解することは極めて重要です。
〈イメージだけで好き、嫌いを決めていませんか?〉
編集部 『「嫌中」時代の中国論』を読んで、これまで勉強不足だったなと実感しました。本書で一番伝えたいことは何でしょうか?
藤野 本の帯にも書きましたけど、とにかくイメージとか感情だけで相手を拒否してしまうことはやめませんか、ということです。単純に好きであればいいのかというと、そうではないですよね。ただただ中国が好きです、というだけではダメなんです。バランスよく見るには、批判的な目線も求められるべきでしょう。もちろん、単に嫌いだ、「中国」という字さえも見たくないというのも、あまりにも極端すぎる。感情の問題はさておき、お互い何らかの形で付き合っていかなければならないのです。江戸時代のように鎖国して長崎だけで付き合うというわけにはいかないんです。とすると、どうしたらうまく付き合っていけるのか、どうしたら軋轢を少なくして関係を築いていけるのか、という現実的な問題を考えていかなければならない。そのためには、ちゃんと日中関係の歴史と現状について理解を深める。そして自分の視点を豊かにしていく。そういう作業が必要です。
基本的に、日本人も中国人も認識のなかで欠落しているのはそこだと思います。そういう現状があるために、余計に日中関係は不安定なものになってしまっている。世論調査をするとそうですよね。国家間関係が悪くなると、すぐ世論調査で国民感情の悪化という結果が出てくる。すごくぶれが大きいわけです。しかし、本質的に中国という国が変わったかというと、昨年と比べて何も変わっていない。日本もそうです。表面的な部分、イメージの部分で流されてしまうと、的確に現状が読めなくなってしまいますよね。そういうのはまずいのではないかと思います。
好き嫌いの感情はともかく、基本的なことを理解しないまま、あの国は嫌いだとかダメだとか言ったって、何の意味もないです。ダメならダメと言っていいけれども、なぜダメなのか、それでどうしないといけないのか、そういうところまで議論が深められなければならない。しかし、感情的な反発のレベルで止まってしまっている。一種の思考停止です。ずっとそこのレベルで止まっている。これでは日中関係の未来は開けてこないですね。
編集部 そうですね。お互いをきちんと知ることが大事ですね。
藤野 ええ。しかし、それがなかなか簡単ではないということですね。少しずつやっていくしかない話だと思います。いま頑張れば、来年にはどうにかなるということではなくて、最低でも20年、30年のスパンで、教育の分野にしろ、メディアの世界にしろ、粘り強く取り組んでいかなければならない問題です。
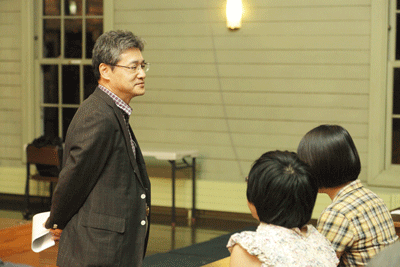
(2013年10月12日「第4回 鈴木邦男シンポジウム」で学生と談笑する藤野彰先生 撮影:小森学)
〈知中派、知日派を育てる〉
編集部 研究者になられたのは若い世代を育てるためですか?
藤野 研究者になったのは別の経緯があるんです。また特派員として中国に出られるとか、これからも報道の第一線で新聞記者を続けていけるという環境があったら、まだ現場のジャーナリストをやっていたと思いますよ。年齢の問題もあるし、新聞社も組織ですから、自分のわがままが通るわけでもないのです。
編集部 今は大学で若い方を育てられていますよね。
藤野 自分のキャリアを生かせる。中国問題、ジャーナリズムの研究を継続できる。若い人たちに自分の経験、知識を伝えられる。いくつかの条件を考えると、大学に移るというのはベターな選択でした。
編集部 藤野先生のような方が、直接若い人たちに影響を与えられるのは、これから日中の理解を深めるためにもいいことですね。
藤野 北海道大学には中国の留学生も多いですから、日常的に「中国」と接触しています。報道の世界と違って個々の相手の顔がよく見える関係ですね。接触を通じてお互いの認識を深めていければいいんじゃないでしょうか。日本人はとかくせっかちなので、中国の政治家みたいに、30年後にどうしようかという発想にならないんですね。だけども、30年後にどうありたいか、どうすべきか、ということを念頭に置いて、いろんな政策を進めていかなければいけませんね。日本人が弱いところはそこだと思います。
編集部 首相が毎年変わっているような状況で、できるのでしょうか。
藤野 そういうふうに不安定な状況だと、余計に全体が近視眼的になってしまいがちですよね。中国は一党独裁ということもありますけど、一つの政権が10年単位で交代していくわけです。10年間続くということは、かなり先々のことまで想定しながらいろんな布石を打てるんですね。だから一党独裁のほうががいいというわけじゃありませんけど。
編集部 政治的な体力が違いますよね。
藤野 それはもう、いろんな物事を決める上でも違いますね。外交上だってそうです。中国の政権が10年間変わらないとなれば、ほかの国は本腰を入れて中国と付き合わざるを得ないわけですよ。交渉だって小手先のものでは済まなくなる。日本みたいに、来年は首相が代わっているかもしれないから、今は適当にお茶を濁しておけばいいというように足下を見られてしまう国では、ね。政治体制が違うので、日本で10年間の長期政権なんていうのはちょっと考えられない話ですけど。
とにかく、いろんな分野で中国と付き合っていくには、長い目で見ていくことが必要です。いま北海道大学に留学に来ている22~23歳くらいの学生たちが20年後にどうなっているか。30年後に中国でどのような分野でどのような職責を担っているか。そういうことを想像しながら育てていくことが大事だと思います。
編集部 今、大学では何を教えてらっしゃるのですか?
藤野 大学院ではメディア論、ジャーナリズム論、学部では中国語のほかに中国問題も教えています。前期は「現代中国入門」という科目を学部生向けに開講しました。日本人だけではなく、中国人留学生もけっこう受講してくれました。
編集部 へえ、外国で自分の国のことを学ぶというのは面白いでしょうね。
藤野 彼らに聞くと、中国で生まれ育ったけれども、自分の国が今どうなっているのかについて実はよく知らない、だからこの授業を取りましたということなんですよ。外の世界の人間は中国をどう見ているか、といったようなことは、彼らにとって興味があるところだと思います。中国の学校では、共産党内部はどうなっているかとか、共産党のこういう政策は間違いだとか、そういうことも教えてくれませんからね。
編集部 留学生はみんな中国に帰るのでしょうか。
藤野 それはいろいろです。日本での就職を希望する留学生も少なくありません。これからの時代はどの国で働こうが、関係ないです。日本で働こうが、中国に戻って働こうが、どちらにいても各人が果たすべき役割というのは当然あるのですから。現実に状況は変わってきています。中国で働く日本人も30年前に比べれば、爆発的に増えてきています。日本人は日本で働かなければならないとか、そういう考えはあってはいけないですよね。中国人も、もちろんそうです。海外華僑・華人の多さを見てもわかるように、中国人は伝統的にそもそもグローバルに動いている人たちですから。
いたずらに中国という国を怖がったり、敬遠したりという風潮はなくなってもらいたいですね。そのためにはどのような国なのかということについて最低限の知識と理解が必要です。それを知ることが今後の日中関係を築いていく前提になりますね。私に今できることは、人々がそういう理解を深めることの手助けですね。大学で学生に教えることもそうだし、今回のような本を世に問うということもそうだし、自分がやっているトータルな活動というのは結局、そういうところに集約されると思います。その意味では、大学という組織の殻に閉じこもることなく、ジャーナリストとしての情報発信を続けていきたいと考えています。
【藤野彰先生の講演会情報】
藤野彰著『「嫌中」時代の中国論』出版記念トークイベント
『「嫌中」時代の中国論』の著者藤野彰氏をお招きして、
異質な隣人・中国とどう向き合うべきか、
お互いの国民が敵視し合う異常な状況のなかで
何を考え、いかに行動すべきかを語っていただきます。
日時:2013年12月7日 15時から
場所:紀伊國屋書店札幌本店 1階 インナーガーデン
札幌市中央区北5条北5丁目 sapporo55ビル
入場無料
*終了後サイン会を予定しております。
【鈴木邦男さんのコラムで紹介されました!】
マガジン9「鈴木邦男の愛国問答」
第136回 「中国といかに向き合うか」を考えた
http://www.magazine9.jp/article/kunio/8865/
【各メディアで紹介されました!】
2013年9月24日 国際貿易 「近着の図書紹介」 書評:亜娥歩
2013年10月13日 日経新聞書評―中国を複眼的にとらえる
http://www.nikkei.com/article/DGXDZO61034990S3A011C1MZC001/
2013年10月13日 北海道新聞 ほん欄
新聞記者時代の経験などもふまえ、異質な隣人である中国とどう向き合うかを解説。
2013年10月25日 週刊読書人 「対中国、いま必要な論議 両国はどのように解決の道を探るのか」書評:朝浩之
中国にどのように向き合えばいいのか、記者の経験を活かしながら多角的に論じている。
「嫌中」であっても「知中」の心は忘れないで欲しいという著者の願いが込められた書。
2013年10月28日 読売新聞 「本よみうり堂」
北京特派員を務めるなど中国で長期間取材してきた著者が具体的なデータを示し、
考えるヒントを与えてくれる。
2013年11月1日号 日本と中国「“日本と中国”を読む」
――単眼ではなく、複眼的思考でとらえる 書評:高橋茂男